北海道に暮らす私たちの、ささやかな特権。
「六花亭」から誕生日プレゼントがもらえるのだ。
誕生日の当日に喫茶コーナーを訪れ、身分証明書を提示すると、ケーキとコーヒーが無料で振る舞われる。
さらに希望すれば、ロウソクに火を灯し、店員さんたちが「ハッピーバースデー」を合唱してくれるという、なんとも温かなサービスだ。
けれど、私はいつも「ロウソクまで」と決めている。
歌まで受け取ってしまうには、私の心臓はまだ人目を気にしすぎて、その真っ直ぐな祝福を受け止める準備ができていないのだ。
ふと、過去三年の誕生日に撮ったケーキの写真を見返してみる。
そこには、数字という記号以上に雄弁な「私」が写っていた。
48歳、まだ「余白」の中にいた頃

そこには、誇らしげにロウソクが立てられたケーキが写っている。 「まだ四十代だし」という、どこか根拠のない余裕が私を包んでいたのだろう。自分へのプレゼントにと、意気揚々と本まで買い込んでいた。
けれど、五十歳になった今も、その本はまだ読み終えていない。 当時の私には、何かを成し遂げようとする「気負い」のようなものがあったのだと思う。その熱は、ケーキを平らげる頃にはもう、静かに冷めていたのかもしれない。
49歳、自意識という名のさざ波

四十九歳のケーキには、ロウソクが一本も立っていない。 確かな理由は思い出せないけれど、たしか、自分からお断りしたのだと思う。
五十という大台を目前にして、私の自意識はひどく落ち着かなかった。 祝われるのが嫌なわけではない。ただ、その一本の火を吹き消すことに、何か決定的な「覚悟」が必要な気がして、臆病になっていたのかもしれない。
ロウソクを立てない代わりに、私は紅茶をゆっくりと啜り、ケーキをひと口ずつ、丁寧に運んだ。 けれど、食後にはしっかりとした「胸やけ」がやってきた。 ああ、もうケーキは当分いいな。そう苦笑いしながら店を後にしたとき、老いという足音が、すぐ後ろまで来ていることを悟った。
50歳、ようやく届いた「おめでとう」

そして、五十歳。 「人生の節目」という言葉が、もはや比喩ではなく、重みを持った事実として響く年齢。
この日、私に「おめでとうございます」と声をかけてくれたのは、六花亭の店員さんだけだった。 若い頃の私なら、それを「マニュアル通りのサービス」と冷めた目で受け流し、勝手に虚しさを募らせていたかもしれない。
けれど、不思議だった。 その一言が、今の私には、驚くほど素直に、温かく胸に染み渡ったのだ。
年を重ねるということは、余計なひねくれを削ぎ落としていく作業なのかもしれない。差し出された善意を、ただ有難く、そのまま受け取る。そんなシンプルで、けれど難しいことが、ようやくできるようになってきた。
人生を八十年とするなら、私にはまだ、三十回ほどの「チャンス」がある。 いつか、周りの目なんて一ミリも気にならなくなったその日には、あの合唱をお願いしてみよう。
「今年もありがとう、六花亭」
揺れるロウソクの火をじっと見つめながら、私はまたひとつ、静かに、そして深く、自分を慈しむように年を重ねた。








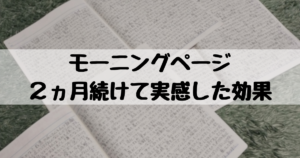


コメント